梅湯流しとは
腸の大掃除特集で、雑誌ゆほびかで梅湯流しが取り上げられました!
雑誌『ゆほびか』のご紹介
『ゆほびか』は、心と体の健康、自然療法、食養生、精神的豊かさなど、「幸せに生きるためのヒント」を紹介する人気健康雑誌です。医師や専門家による実践的な健康法から、読者の体験談まで幅広く掲載され、健康意識の高い読者に支持されています。
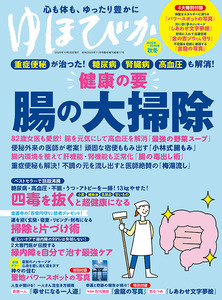
特集:「腸の大掃除」で腸をすっきりデトックス
今回の特集では、島袋史がインタビューをうけて、腸のデトックス方法の1つとして、
梅干しと大根煮汁を使ったデトックス法「梅湯流し(うめゆながし)」が紹介されました。便秘や肌荒れ、疲れ、むくみなどを感じる人におすすめの、腸を浄化する自然療法です。
◆ 梅湯流しとは
「梅湯流し」は、梅干しのクエン酸と大根煮汁を使って、腸内の老廃物を自然に排出する方法です。腸を刺激してぜん動を促し、宿便や毒素をスムーズに出すことで、体が軽くなり、肌つやもよくなるといわれています。
- 宿便や老廃物の排出を促す
- 肝臓や腸の働きを整える
- 疲労や肌荒れの改善
- 代謝・免疫力アップ
腸にたまった便を出し切るお勧め姿勢は考える人のポーズ
梅湯流しをしてもスッキリ出ないときに、体勢を工夫して腸の動きを助けます。
- 食事のタイミングを逃さない: 朝食後など腸が動くタイミングを活かす。
- 便意を感じたら我慢しない: 便意を逃さずすぐにトイレへ。
- 梅湯は予定のない日に行う: ゆったりした気持ちで取り組むことが大切。
出典:雑誌『ゆほびか』2025年9月号掲載記事より
⑴「梅湯流し」はどのような体調の人、悩みがある人におすすめできますか? 反対にやってはいけない人についてもお聞かせください。
体調が悪かったり、悩みがある人も、体調が良い人も全ての人にお勧めです。梅湯流しは、断食とセットなので、やってはいけない人は、糖尿病でインスリン注射を行っていたり、他に何らかの持病が有り、治療を行っている人などの場合には、主治医に断食をして良いか相談する必要があるかと思います。また、胃潰瘍の場合には、断食は行っても、クエン酸の刺激が良くないので、梅湯流しはせずに、復食に野菜をしっかり摂るようにします。また、消化器にトラブルがある場合にも主治医に相談した方がよいでしょう。様々な持病がある方達にも断食と梅湯流しはお勧めではあるのですが、持病がある場合には主治医に相談してから行うようにお勧めします。
⑵ 「梅湯流し」はなぜ、便秘の解消に効果があるのでしょうか。
食を断って、クエン酸をたくさん含んだ梅干しを使うことで、腸のぜん動運動を高めて、便秘解消が出来ます。便秘と思っていなくても便塊がたまっている人が多いのです。
関連コラム(お尻便秘について)
⑶梅湯流しはどのくらい断食をしたらよいですか?
なるべく胃腸を空にして、梅湯流しをしないと、腸洗浄の効果が得られないです。一食だけ食事を抜くのであれば、前日の夕食は早めにすませて、朝食をぬいて、お昼から梅湯流しを行う方法もあります。この場合に、洗浄まで出来るかは分かりませんが、何度も、間を開けながらもつづけていくことが大切です。また、大切なのは、梅湯流しの後の食事(復食)が良いものでないと、かえって、胃腸の調子を悪くするので、梅湯流しをした後の食事は、悪いものを摂らないようにしましょう。腸内環境を良くしていくようにしましょう。
関連コラム:腸内環境を良くして、健康でいるためにするべきこと。
⑷「梅湯」の作り方について。
大根の煮汁がしっかりでるくらいで、特に決まりはないのですが、私はいつも保温鍋で沸騰したら火をとめて、1時間ほどで使っています。時に、そのまま2,3時間放置することもありますが、保温鍋は数時間おけるので問題ないです。短時間で食べたい場合、沸騰して10分くらいしたら十分だと思います。
⑸たとえば「梅湯」をどんぶり3〜4杯(1200ml程度)全部飲み干せない人はどうしたらいいでしょうか?
梅湯のお湯の量は体格にあわせて増減させます。どんぶり2杯くらいから4杯くらいと自分の体格にあわせて調整して良いです。
⑹ 排便の際、気をつけることはありますか? 腹痛や便の状態など、梅湯流しをしてよいのか心配です。
梅湯流しの場合に、何度も軟便がでるので、トイレットペーパーで肛門をこすらずに、押さえるようにするか、水で流すなどで汚れを落とすのと、無理に息まないようにする。ただし、頻繁にシャワートイレで洗い流すのも肛門粘膜への刺激が強すぎて粘膜に炎症を起こしてしまう可能性があります。(参考:お尻は洗っちゃだめ!)洗う場合も水で軽く流す程度にしましょう。梅湯流しをしたあと、便意を催したらすぐに、その機を逃さないようにトイレに行きましょう。排便の際には少し膝をあげて、状態をかがめて(彫刻考える人のポーズをイメージして、便を出すと良い。少し前掲して足下に踏み台を置いて少し膝を高くすると良いです。また、排便時には無理に息まずに、臍の下をマッサージ、左下腹部を指圧する。深呼吸をするなどを行いましょう。
⑺「梅湯流し」の完了後、食生活を戻していく際、気をつけることを教えてください。
断食の期間だけ復食期間を設けた方が良いです。1日断食したら、一日は、腸によいと言われる物をとって、身体に悪い物は摂らないようにしましょう。3日断食したら、復食に3日は必要です。
断食明けには、野菜(芋類・豆類は控えめに)、アボカド・きのこ類・十割そば(油・砂糖・動物性の出汁不使用)、果物(酸味や糖分が少ないもの)、豆腐・納豆・麩・こんにゃく、海藻・豆乳・カフェインなしのお茶)などは摂っても良いです。
だんじき明けには、次の物は避けましょう。油・砂糖・魚貝類・卵・もち、ナッツ類・ごはん・みりん・香辛料、せんべい・にんにく・からし(生姜・わさびは可)、長芋・アイスクリーム、生のパイナップル、コーヒー・緑茶・炭酸飲料 これらは避けた方が良いです。
⑻「梅湯流し」をお勧めする理由について教えてください。
梅湯流しをお勧めするというか、断食をお勧めします。断食によって、身体は休むことが出来ます。常に食べ物が入ってきて、胃腸は休む暇も無いですが、胃腸にお休みをあたえて身体を回復させることで、本当の疲労回復につながります。断食をして、梅湯流しを行うことで、身体の浄化が完成します。断食で、腸管免疫が活性化する 善玉菌が蘇ります。その結果、腸管免疫(特に自然免疫)は活性化、疲労回復効果;「ケトン体がエネルギーになること」が挙げられます。ケトン体がエネルギーになると、ミトコンドリア系のエネルギーが稼働し始めます。解糖系エネルギーの19倍ものエネルギーが出るようになります。細胞の働きが活性化する:断食を行うと血流が極めて良くなり、細胞の働きが活性化していきます。長寿遺伝子の活性化・・・延命につながる、精神面の安定化、微小循環の改善と体温の上昇・・・手足冷え改善、様々な断食の健康効果があり、その後に梅湯流しで腸内洗浄をして、その後の復食で腸に良い食べ物ををいれてあげることで、劇的な腸内環境改善が期待できます。ただし、長年の身体の汚れは数回の断食と梅湯流しでは改善出来ないことも多いので、すぐに効果が得られなくても、継続していくことが大切です。
梅湯流しの梅の注意点について教えてください。
梅干しに入っている酸味のもと、クエン酸が少ない梅干しを使うと思ったような効果が得られない場合があります。梅流しには梅干しは昔ながらの酸っぱい梅干しを使用しましょう。市販の梅干しには、人工甘味料や保存料などの添加物がたくさん含まれています。できるだけ、塩と紫蘇だけで作られた梅干しを使いましょう。
ネットで購入できる無添加梅干し:かわしま屋
梅湯になぜ大根煮汁を組み合わせるの?
梅湯の働き(梅干し+お湯)
- クエン酸:疲労回復、胃酸分泌を整える、殺菌効果
- アルカリ性食品:体内の酸性状態の中和
- 胃腸の目覚まし:お湯に溶けた梅の有機酸が、弱った胃腸をやさしく刺激
- → 断食後の回復や、食べすぎ・毒素の排出をサポート
大根煮汁を加える意味と効果
| 主な理由 | 内容 |
| 🧼 腸の洗浄効果 | 大根の煮汁には、**水溶性成分(酵素・苦味成分)**が溶け出しており、腸の蠕動運動を促進。宿便やガスの排出を助ける。 |
| 🔥 消化を助ける | 大根に含まれるジアスターゼや他の酵素類が、胃腸の消化機能をサポート。重い胃を軽くする。 |
| 💧 デトックス+利尿効果 | カリウムや食物由来の利尿成分で、体にたまった水分や毒素を排出しやすくする。 |
| 💡 温性の水分補給 | 温かい煮汁は胃腸を冷やさず、水分・ミネラル補給にもなる。特に断食中・回復期には重要。 |
梅湯だけでは足りない点を補う
梅湯単体でも軽いデトックス効果はありますが、
- 腸の物理的な動きを促す力
- 便通を促す作用
- 胃腸の消化力そのものを支える栄養素
などは弱いため、大根煮汁を加えることで実際の「流し出す」力が増すというのがポイントです。
✅まとめ:なぜ梅湯に「大根煮汁」を加えるのか?
| 梅湯の役割 | 大根煮汁の役割 |
| 酸性の体を整える | 消化を助け、腸を動かす |
| 胃腸に優しい目覚まし | 宿便や毒素を「流す」 |
| クエン酸で疲労回復 | 食物由来の利尿・解毒 |
→ 梅湯+大根煮汁の相乗効果で「腸のリセット・体内の大掃除」が実現する
梅干しと大根湯でなければいけないのですか?
大根は冬場の食べ物なので、夏は値段が高いし、季節の野菜でもありません。そこで、夏野菜の冬瓜で梅湯流し出来ないか試してみました。効果に関しては、大根と大きな違いは感じませんでした。また梅干しを食べるだけでなく、梅湯にする理由は、梅干しだけだと、刺激が強すぎるのと、胃腸に行き渡りにくいという理由があります。梅干しは腸内を殺菌する食べ物としては一番よいです。クエン酸含有量はレモンの5~6杯です。
梅湯流しにかかる時間は?
個人差がありますが、1時間から3時間くらいでは、排泄が終了します。梅湯を飲み終わって40分から1時間の間には、排泄が始まります。大体、3~5回程度で終わります。
「腸と森の「土」を育てる」桐村里紗著
腸内環境を畑にたとえて、便秘で、土壌が水分不足でかちかちだと、雨が降っても土は水を吸収しないで洪水になる(便秘と下痢繰り返す)、きちんと土をたがやして、ふかふかの畑にしてあげましょう。
断食について
まとめ
梅湯流しは、手軽で体にやさしい自然療法として人気があります。
食べすぎ・飲みすぎ・疲労がたまったときや、季節の変わり目に行うと、
腸が軽くなり、体全体の調子が整いやすくなります。
無理せず、自分のペースで続けることがポイントです。



